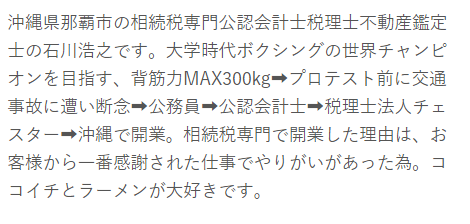沖縄県で相続税の相談をするなら
那覇円満相続相談センター
運営:石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所
〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1-1-25-2622
受付時間 | 平日:10:00~18:00 |
|---|
定休日 | 土・日・祝 |
|---|
相続時精算課税制度を沖縄の相続専門税理士が解説
2020/3/14(2025/6/29更新)

沖縄で相続時精算課税制度を使った生前贈与を検討している方向け。
周りで相続時精算課税制度を使ってる人が多いけど
- 相続時精算課税制度って何なの?
- 使う為にはどうしたらいいの?
- メリットやデメリットはどんなことがあるの?
と思っている方に、【初心者向け】相続時精算課税制度の概要から計算の仕方まで簡単に解説します。

所長 石川 浩之
【この記事の執筆者】

相続時精算課税制度は、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与をすることができるのですが、その名の通り、相続の時に精算してくださいねという贈与税の特例の制度です。
相続時精算課税制度を理解するポイントは、下記の3つです。
1.財産をあげる人ベースで考える
2.一度相続時精算課税制度を使うと元の暦年課税制度には戻れない
3.相続の時に精算される
①財産をあげる人ベースで考える
贈与税は財産を貰った人ベースで贈与税の計算をしますが、相続時精算課税制度という特例を使うかどうかは、財産をあげる人ベースで考えます。
したがって、お父さんからの贈与は相続時精算課税制度を使って財産を贈与して貰い、お母さんからの贈与は通常の暦年課税制度を使って申告するということが可能です。
②一度相続時精算課税制度を使うと元の暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度は一度使ってしまうと、通常の暦年課税制度に戻ることができない決まりになっています。
したがって、2,500万円の非課税枠を使い切ったから今後は暦年課税制度で贈与していこう!と考える方が非常に多いのですが、残念ながらできませんのでご注意ください。
③相続の時に精算される
本来贈与とは、財産をタダであげることを言う為、贈与をすると財産を貰った人の財産になります。
したがって、贈与をした人の財産が減少する為相続税対策になりますよ!という話なのですが、相続時精算課税制度を使うと、相続の時に贈与が無かったものとして相続財産に足し戻されてしまうという性質を持っています。
また、贈与が無かったものとして相続財産に足し戻される時の金額は「相続時の時価」ではなく、「贈与をした時の時価」というルールになっています。

沖縄では相続時精算課税制度が流行っているらしく利用されている方が多いです。
友人・知人からの話を聞いて、私も相続時精算課税制度を使いたい!と依頼が来ることもありますが、相続時精算課税制度を使う為には要件があります。
要件のポイントは下記2つです。
1.適用できる人が限定されている
2.書類提出が必要
①適用できる人が限定されている
財産をあげる人と財産を貰う人の両方に要件があります。
| 財産をあげる人 | 財産をあげた年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん)であること |
|---|---|
| 財産を貰う人 | 財産を貰った年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(お子さまやお孫さま)である推定相続人か、お孫さまであること |
ややこしいですね。
養子縁組やお子さまが既にお亡くなりになっていて代襲相続の話があったりするともっとややこしい話が出てきたりします。
また、個人や法人の事業承継税制を使う場合には、20歳以上であれば直系卑属じゃなくても使える等はあるのですが、
細かいことは置いといて、
60歳以上のご両親やおじいちゃん・おばあちゃんから18歳以上のお子さま・お孫さまに贈与する場合に使えるのだなと思っていただければと思います。
レアケースの場合は、面談の際にきちんと状況を伺い、相続時精算課税制度を使えるかどうか説明いたしますのでご安心ください。
②書類提出が必要
じゃあ、適用できる人に該当してたらどうやって使ったらいいの?となりますよね。
結論としましては、贈与税の申告書に相続時精算課税制度を使いたいです!という申請書を添付すればOKです。
110万円以下の贈与の場合は、贈与税の申告書の提出が不要のため、相続時精算課税制度を使いたいです!という申請書を提出すればOKです。
具体的には、
- 相続時精算課税選択届出書
- 財産をあげる人と財産を貰う人の戸籍謄本(抄本)
です。
相続時精算課税選択届出書
これは通常の暦年課税制度ではなく、相続時精算課税制度を使いたい(選択したい)です!という申請書です。
この用紙を埋めていけば必要書類も書いてあるので、相続時精算課税制度を使った方が良いかどうかの判断は別として、申請自体は税理士に頼まなくても可能だと思います。
財産をあげる人と財産を貰う人の戸籍謄本(抄本)
戸籍謄本で何を確認するかと言うと、財産をあげる人と財産を貰う人が要件を満たしているかどうかです。
| 財産をあげる人 | 財産をあげた年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属(ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん)であること |
|---|---|
| 財産を貰う人 | 財産を貰った年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属(お子さまやお孫さま)である推定相続人か、お孫さまであること |
したがって、戸籍謄本で
- 財産をあげた人の生年月日から1月1日時点で60歳以上かどうか。
- 財産を貰う人から見て、直系尊属(ご両親やおじいちゃん・おばあちゃん)に該当するかどうか。
- 財産を貰う人の生年月日から1月1日時点で18歳以上かどうか。
を確認します。
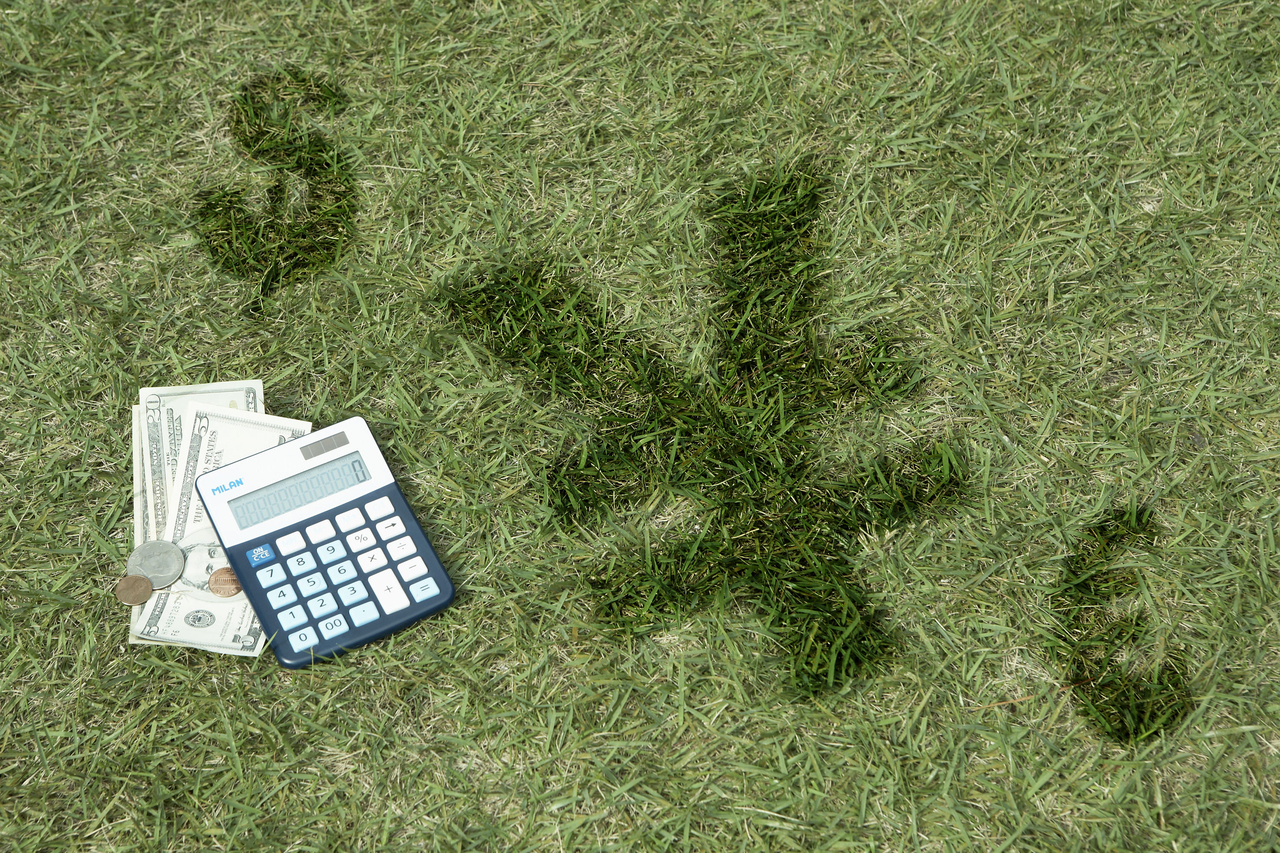
相続時精算課税制度を使った場合の、贈与税額の計算は3段階で考える必要がありますが、慣れれば簡単です。
①基礎控除(毎年110万円まで)
毎年110万円までの贈与➡0円、贈与税の申告は不要です。
②特別控除(生涯で2,500万円まで)
①の枠を超えた部分が②の枠に入ります。
合計2,500万円までは贈与税がかかりません、贈与時絵の申告が必要です。
③特別控除を超えた部分
①と②の枠を使い切った後の贈与は一律20%の贈与税がかかります。
この時に支払った贈与税は、将来の相続税から差し引くことが可能(相続税の前払い)です。
3,000万円贈与した場合
(3,000万円-110万円-2,500万円)×20%=78万円
1億円贈与した場合
(1億円-110万円-2,500万円)×20%=1,478万円

前述した通り、沖縄では相続時精算課税制度が流行っていますが、2,500万円まで贈与税無しで贈与できるなんてお得だね!と良いところしか見てない印象があります。
相続時精算課税制度に限ったことではありませんが、メリットもありデメリットもあります。
代表的なメリットを3つとデメリットを5つ簡単に説明します。
メリットだけではなくデメリット部分も踏まえてトータルで判断した上で、相続時精算課税制度を使うのかどうか検討して頂きたいと思います。
メリット
①110万円以下の贈与は贈与税の申告が不要で、将来の足し戻しも不要
暦年贈与の場合、お亡くなりになる直前7年間の贈与はなかったものとして、相続財産に足し戻される結果、相続税がかかります。
しかし、相続時精算課税制度を使った贈与の場合、お亡くなりになる直前7年間の贈与でも、相続財産に足し戻す必要がなく、完全に非課税で財産を渡すことが可能です。
②贈与時の価格で固定できるため、値上がりする財産に効果的
相続時精算課税制度を使うと、贈与で財産を渡しているものの、相続の時に精算するため実質相続財産は減っていないものと考えられます。
ただし、相続の時に精算する金額は「相続の時の時価」ではなく「贈与した時の時価」のため、値上がりする財産の場合に効果的です。
たとえば贈与の時に2,500万円の価値でしたが、相続の時に仮に1億円の価値になっているとしたら、相続財産に足し戻される金額は1億円ではなく2,500万円で済むので、値上がり分の7,500万円がまるまる相続税対策をしたことになります。
また、収益を生み出すような財産の場合には、その後の収益をお子さまやお孫さま等に移すことが可能です。仮に値上がりしていなくても相続税対策になる場合があります。
③そもそも相続税がかからない人は非課税の2,500万円を使って早期に財産を譲ることができる
相続時精算課税制度を使わずに暦年課税制度を使って一度に2,500万円を贈与すると、一般税率の場合は945万円、特例税率の場合は810.5万円と多額の贈与税がかかります。
相続時精算課税制度を使うと相続の時に贈与時の財産の価格が足し戻されてしまう訳ですが、元々相続税がかからない場合には、相続財産に足し戻されたところで相続税が0のため、相続を待たずに早期に財産を譲ることが可能です。
④贈与税は必ず精算される
相続時精算課税制度を使って贈与税を支払った場合、相続の時に精算するのが前提のため、贈与税>相続税の場合でもお金が戻ってくるのが特徴です。
たとえば、相続税100万円で贈与税500万円を支払い済みの場合には、相続税100万円-贈与税500万円=△400万円が精算されてお金が戻ってくるのです。
暦年課税の場合は、お亡くなりになった直前3年間の贈与が無かったものとして計算され、相続税から贈与税を差し引く制度がありますが、贈与税>相続税の場合に贈与税がは残念ながら贈与税が戻ってこないです。
相続税100万円で贈与税500万円を支払い済みの場合には、相続税100万円-贈与税500万円=相続税0円となり、相続税を支払う必要はありませんが、贈与税400万円は戻ってこないのでご注意ください。
デメリット
①暦年贈与に戻ることができなくなる
最初の概要でお伝えした内容になりますが、相続時精算課税制度は一度使ってしまうと、通常の暦年課税制度に戻ることができません。
2,500万円の特別控除を使い切ったので、暦年贈与に戻したいと思っても残念ながら暦年贈与に戻すことはできないのでご注意ください。
②小規模宅地の特例が使えなくなる
これは少しややこしいお話になるのですが、小規模宅地等の特例という土地の評価を安くしてあげますよ!という特例が使えなくなってしまいます。
小規模宅地等の特例とは何かという話は別途記事を書きたいと思いますが、簡単に説明すると一定の要件を満たした土地については、最大8割引き!で2割の評価にしてあげますよ!という特例です。
小規模宅地等の特例の要件の1つとして、相続または遺贈(遺言で財産を貰うこと)で財産を取得する必要があるので、贈与(相続時精算課税制度)を使って取得した財産については、小規模宅地等の特例が使えないことになっています。
③相続の時に必ず足し戻される
15年前に相続時精算課税制度を使ったけど、そんな昔のことは税務署は分からないよね?と質問してくるお客さまがたまにいらっしゃいます。
残念ながら
100%バレます!

相続時精算課税制度を使って申告をすると、税務署は財産をあげた人がお亡くなりになるまで10年でも20年でも50年でも保管しています。
税務署は内部資料から相続時精算課税制度で贈与した財産が、相続税の申告書にきちんと載っているかどうか必ず確認しています。
相続税の申告書に載っていなかった瞬間に財産の申告漏れが確定しているので、100%の確率で税務署から指摘がされて無駄な追徴課税(ペナルティ)が発生します。
財産を隠すのは節税ではなく脱税です、どうせ税務署は分からないだろうと思って隠すのは辞めましょう。
非常に細かい論点として、平成21年12月31日までに相続時精算課税制度を使って住宅取得資金の贈与が非課税になる特例を使った場合には、相続財産に足し戻して計算するという制度もあり、相続時精算課税制度の中でも特に漏れやすい注意点があります。
④相続の時よりもコストがかかる
相続時精算課税制度に限った話ではないのですが、贈与で財産を渡すと相続で財産を渡す場合と比較してコストがかかってしまう場合があります。
2,500万円まで贈与税がかからないんでしょ?と言われればその通りなのですが、不動産を贈与する場合、不動産取得税や登録免許税も加味してトータルで考えなければいけません。
細かい内容を書くと長くなってしまう為、ざっくり概要をまとめると下記の通りです。
| 相続 | 贈与 | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | かからない | かかる(1.5~4%) |
| 登録免許税(名義変更の税金) | 0.4% | 2% |
相続で不動産を取得する時は不動産取得税がかからないですが、贈与で不動産を取得する時は不動産取得税がかかります。
じゃあ、どのくらいかかるのか?というと、贈与する財産が土地なのか建物なのかで金額が違ったり、建物も築何年なのかによって異なりますし、地域によっても異なります。
仮に2,500万円の建物(住宅)で控除額を無視して計算すると2,500万円×3%で75万円の不動産取得税がかかることになります。
更に、贈与をしたことにより登記の名義変更にかかる税金が2,500万円×2%=50万円かかります。
相続で財産を取得していれば2,500万円×0.4%=10万円で済んだため、名義変更だけで40万円も税金が高くなってしまいます。
もちろん、不動産取得税75万円+登録免許税の増加40万円=合計115万円を上回る相続税の節税メリットがあれば良いのですが、元々相続税がかからない方なのに贈与税がかからないからと言って、わざわざ115万円の無駄な税金を支払ってるケースが残念ながら沖縄ではよくあります。
贈与税という狭い視野だけで判断するのではなく、その他のコスト(不動産取得税や登録免許税、税理士費用、司法書士費用等)も加味して考えないと後で100万円以上損するかもしれません。

相続時精算課税制度について簡単に解説してみましたが、いかがでしょうか。
沖縄では相続時精算課税制度が流行っていますが、周りの友人・知人からの紹介でデメリットを考えていないため、後で損する方が非常に多いです。
大がかりな贈与をする時は、一度現状分析をすることをおススメしております。
このコラムについても、コラムという性質上細かい要件を全て網羅している訳ではございません。
餅は餅屋です。
当事務所は相続税を専門に扱っているので、贈与税申告を含めた相続税対策の豊富な経験・ノウハウがございます。
節税はもちろん、円満に仲良く相続していただくことの大切さをお伝えし、お客さまの幸せで円満な相続と節税の両立をサポートさせていただきます。
沖縄で相続税(節税)対策は相続専門の石川公認会計士事務所にお任せください。
関連するページのご紹介
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
サイドメニュー
- 相続税の計算
- 相続税の基礎控除を解説|相続税はいくらからかかるの?
お客さまの声
親切で分かりやすく、良心的な価格のサービス

30代女性 Aさま
こちらが不安に思っていた部分も気軽に相談・質問できて胸のつかえがとれました。
お勧めしたいサービス

40代男性 AKさま
些細なことでも親身に相談に乗っていただき、大変心強かったです。また、二次相続対策についても、分かりやすく説明していただき、周りに相続で困っている人がいたら、ぜひ石川先生を紹介させていただきたいと思います。
石川公認会計士・税理士・
不動産鑑定士事務所

住所
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち1-1-25-2622
アクセス
ゆいレール「おもろまち」駅徒歩6分
サンエー那覇メインプレイス徒歩4分
受付時間
平日:10:00~18:00
定休日
土・日・祝
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
(業務エリア:沖縄県全域)